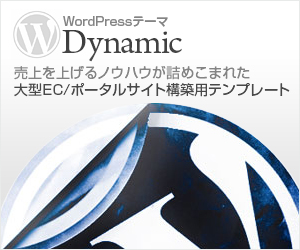社会人のビジネスマナー~話し方のマナー~

本日ご紹介します記事は『話し方のマナー』です。
みなさんは、ビジネスシーンの「話し方」と聞いて何を思い浮かべますか?
今、あなたの頭の中に浮かんでいるのは、お客様や上司との会話、同僚との会話でしょうか。
自分の気持ちを自分の言葉でしっかりと相手に伝える事、
また、相手の気持ちを理解する事は、公私を問わず非常に重要な事柄といえます。
今回も、具体的な例も織り交ぜながら『話し方のマナー』について、ご紹介したいと思います。
1.会社の呼び方
一般的に相手の会社の事は「御社」言い、文章では「貴社」と書きます。
◎自社の事を言う時
「当社」「わが社」
◎外部の人に向かって言う時
「当社」「弊社」
◎謙譲語
「わたくしども」
また、外部の人に第三者の他社の事を言う時は
「○○会社さん」とさん付けで呼ぶ習慣があります。
2.一般的なビジネス敬語
【ビジネス敬語一覧】
・ぼく、わたし ⇒ わたくし
・わたしたち ⇒ わたくしども
・誰 ⇒ どなた様
・あの人 ⇒ あの方、あちら様
・今 ⇒ ただ今
・さっき ⇒ 先ほど
・多分 ⇒ おそらく
・あとで ⇒ のちほど
・少し、ちょっと ⇒ 少々
・どうしますか ⇒ いかがなさいますか
・いいですか ⇒ よろしいでしょうか
・すいません ⇒ 申し訳ございません
・すいませんが ⇒ 恐れ入りますが
3.自分・相手の呼び方
【社内の人へ】
同僚を社内の人へ ・・・ ○○さん
後輩、部下を社内の人へ ・・・ ○○さん
直属の上司を社内の人へ ・・・ 課長、部長、○○課長、○○部長
社長の事を社内の人へ ・・・ 社長
【社外の人へ】
自社の社員の事を社外の人へ ・・・ ○○(よびすて)、課長の○○、部長の○○
先方の社員を社外の人へ ・・・ ○○課長、○○部長、課長さん(様)、部長さん(様)
先方の社長を社外の人へ ・・・ 社長、○○社長、社長さん(様)
自社の事を社外の人へ ・・・ 当社、わたくしども、弊社
先方の会社を社外の人へ ・・・ 御社、貴社
同業他社などを社外の人へ ・・・ ○○社さん
4.間違えやすい尊敬語・謙譲語
<駄目な例文と正しい文章>
(例)「お送りした資料は、拝見されましたか?」
「拝見」は自分がへりくだる時に使う謙譲語です。
正しい ⇒ 「ご覧いただけましたでしょうか?」
(例)「この件は、存じていましたか?」
「存ずる」も謙譲語です。
正しい ⇒ 「ご存知でしたか?」「知っておられましたか?」
(例)「いつ、こちらに参りますか?」
「参る」は謙譲語。
正しい ⇒ 「おいでになりますか?」「いらっしゃいますか?」
(例)「課長が部長に申されたあの件ですが」
部下が上司の行動を謙譲語で表現するのはおかしいです。
(課長自身が、「私が部長に申し上げた」は良い)
正しい ⇒ 「課長が部長にお話になった」又は「課長が部長におっしゃった」
5.上手く話せない原因と対策
~フレーズを覚えておこう!~
上手く話せないのは、緊張から来る事が多いです。
慣れない言葉使いを、無理して使おうとすると余計に緊張します。
ビジネスでの話し方には、パターンがあるのです。
ですので、自分の上司や先輩の話し方をよく観察して、そのパターンを身につけましょう。
パターンを身につけるには、よく使うフレーズをマスターする事が近道です。
こんな時はこう応じるというフレーズを前もって覚えておけば、
どんな質問にも、慌てずに落ち着いて対応する事ができます。
また、相手の話をちゃんと“理解する”という事も大切です。
相手が何を伝えたいのか、何を知りたいのか、何を求めているのかを考え、
それに応じて、自分も相手に伝わるように答えましょう。
6.マイナスイメージとなる過度の謙遜
日本語の慣習的なフレーズは、自分を劣ったものとして表現されるものが多いですが、
逆に過度の謙遜は、相手へのマイナスイメージとなる場合があるので注意が必要です。
また、気をつけなければならないのは相手が心配になるような社内の悪口や問題です。
「まだ慣れないもので・・・」と言って一人前の仕事ができれば良いですが、
言い訳にしか聞こえないような仕事振りでは、次の仕事は無いでしょう。
4.ビジネスの会話で重要な事
どうして上手く話せないんだろう・・・。そう悩むのはまだ早いです!
経験が足りない人が、初めから上司や先輩達のように話をする事は難しいです。
まずは、相手の話をよく聞く「聞き上手」を心がけましょう。
そこで「聞き上手」のポイントとして、2つを下記にあげます。
(1)話している相手に対し、あいづちをうったり、うなずいたりこちら側がしっかりと聞いている姿勢を見せましょう。
(2)自分の言いたい事があっても、相手の話を折ってはいけません。
実はこの「聞き上手」がビジネスを成功させる第一歩でもあるとともに、
顧客から好かれるのは「聞き上手」である事が多いのです。
Check!